そっくりな代替食は必要?小学生になると「食べない事」の意外な落とし穴が…

卵を使わない、本物そっくりのオムレツを見たことがあります。「すごい!」と思った私ですが、同時にこうも思いました。「そこまでしてオムレツ食べなくても…」。
そこには、まず私の料理の腕の問題があります。得意なお母さんなら楽しみながらできる事が、不得意なお母さんには大きな負担になります。
子どもが喜ぶと分かっていればするかもしれません。しかし、オムレツの存在を知らない我が子が喜ぶだろうか…と思った時、そこまでの手間をかけてする気にならなかったのが事実です。日々のアレルギー対応食、アレルギーっ子だけでなくその兄弟のこと、皮膚の症状、鼻炎の症状、学校や幼稚園の事、家の事が加わり、「私には無理だ」と思ったわけです。
しかし、その数年後、思わぬ形でしっぺ返しを食らう事になりました。
小学1年生の国語で…
次男が小学校に入ってすぐの事です。
1年生と言えば授業は大半が「こくご」と「さんすう」。中でも「こくご」に多くの時間が割かれ、毎日、ひらがなやカタカナを習ってきます。
ある日宿題に出されたプリントが分からないと困り顔の次男がやってきました。
国語のプリントの問題には、様々なイラストが描かれており、何の絵かをカタカナで答えるようになっていました。
そこに描かれていたのが、そう、「オムレツ」だったのです。
オムレツの存在を知らなければ当然答える事はできません。
アレルギーっ子はカタカナの食べ物に触れ合えない
こうした問題はその後も何回もありました。彼は「カステラ」も知りませんでした。カタカナは海外から入ってきたものを表すための言葉です。身近な物でカタカナであらわされるものと言えば、食べ物が増えます。海外から入ってきた食べ物には、卵や乳や小麦が使われています。
アレルギーっ子は、カタカナの食べ物に触れる機会が少ないのです。
その時になって思いました。
「食べられないから知らなくていい」のではなく「食べられなくても知っておくこと」が大切だと。
この時から食べ物については逐一説明するようにしていますが、そっくり代替食を作っているお母さん方にはこの問題は起きなかったのだろうと思います。
料理が不得意でも…
数年前に戻れたとしても、やっぱり私は「そっくり代替食」は作れないでしょう。でも、少なくとも「ぐりとぐら」の絵本を読めば、カステラについてしっかりと説明してあげたでしょうし、オムレツについて話をしてあげるでしょう。
当時の私は「説明したら食べたがる」ことも恐れていた気がします。しかし、知らないことよりも、知っていることがやはり大切なのだと今は思います。誤食のことを考えてもそうですよね。
息子は、ブリの照焼きが大好物で、お味噌汁は麦みそ派で、朝昼晩と和食漬けで育ってきました。体のためにも、和食を続けようと思います。その一方で、世の中は洋食が隆盛を誇っている事、忘れずにいたいなと思った出来事でした。
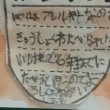
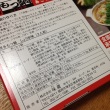






















Your Message